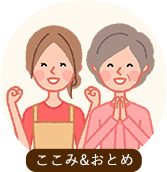公開日: |更新日:
シックハウス症候群への対策方法は?
住む人の健康に配慮した住宅を建てる際、シックハウス症候群という言葉をよく耳にしますよね。では、シックハウス症候群とはどんな症状なのでしょうか?そして、住宅とどのような関係があるのでしょうか?
シックハウス症候群について
医学的には、シックハウス症候群は単一の病気ではなく、居住に由来する健康障害の総称として扱われています。
シックハウス症候群の代表的な症状は、「目のかゆみや赤み」「咳」「めまい」「頭痛」「疲れやすい」「皮膚のかゆみや湿疹」など。
そして、シックハウス症候群の原因は、「建材や調度品などから発生する化学物質」のほか、「カビやダニなどによる室内の空気汚染」であるといわれています。化学物質やカビやダニの多い室内環境で過ごすことで、アトピーや喘息などを発症するリスクがあるのです。
シックハウス症候群になりやすい人の特徴
国立大学法人千葉大学の調査によると、「喘息やアレルギー疾患のある人は疾患歴のない人と比較して1.41倍シックハウス症候群になりやすい」というデータがあります。
また、「カーペットがある場合は1.48倍」「ホコリをよく目にする人は1.56倍」というデータも。つまり、個人の特徴や生活スタイルによって、シックハウス症候群のリスクが高まるのです。
なお、住宅の化学物質を低減した場合、シックハウス症候群のリスクは0.77倍になるのだとか。注文住宅の新築時にシックハウス症候群対策を行うことで、居住による健康障害のリスクを抑えることができます。
参照元:国立大学法人千葉大学|「シックハウス症候群」経験しやすい人や環境の特徴を算出
(https://www.chiba-u.jp/news/research-collab/rpost_131.html)
シックハウス症候群の対策は?
化学物質の発散が少ない建材を選ぶ
シックハウス症候群のリスクを低減させるためには、化学物質の発散が少ない空間にすることが大切。そのため、ホルムアルデヒドの発散が少ない建材を選びましょう。
ホルムアルデヒドの発散が少ない建材かどうかは、「F☆☆☆☆」といった等級で確認できます。ホルムアルデヒドの発散が最も少ない等級は「F☆☆☆☆」であり、発散量が多くなるほど星の数が減っていきます。
また、化学物質の含有状況を知ることも大切。建材の化学物質含有状況は、SDS(安全データシート)にて確認できます。SDSは、事業者が化学物質や製品を提供する際に、取引先である他の事業者へと渡ります。SDSには指定化学物質の組成や含有率などが記載されており、施主がメーカーから取り寄せることができます。
換気システムの採用
シックハウス症候群のリスク低減には、換気も重要なポイント。室内の換気が不十分な場合、湿気がこもり、シックハウス症候群の原因となるカビや細菌が繁殖しやすくなります。
十分な換気を確保するためには、換気量や換気回数を参考にしましょう。換気量とは「1時間に何m2の空気を取り入れるか」、換気回数とは「1時間にその部屋の容積の何倍の空気を取り入れるか」を表すもの。また、換気効率も大切なポイントです。換気量を確保していても、換気効率が悪いと外気が隅々まで行き渡りません。そのため、給気口と排気口を離して設置するようにしましょう。
さらに、換気システムを正常に稼働させるために、メンテナンスも重要です。定期的な清掃を行い、必要に応じて部品交換なども行いましょう。
参照元:国土交通省|建築基準法に基づくシックハウス対策
(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/sickhouse-R4.pdf)
栃木でおすすめの
注文住宅メーカー3選
スムーズな家事動線と
快適な空間を両立したいなら

-
家事の負担を減らす
動線&収納設計
女性ライフプロデューサーのヒアリングをもとに、オープンキッチンや最小限の移動距離を意識した動線設計を提案。収納にもこだわり、片付けやすい住まいを実現。 -
「ライフスタイルに合わせて、
住みやすい設備を自由に
選べる」
キッチン・バスルーム・内装建材など、10社以上・1,800種類以上の住宅設備を標準仕様で選択可能。フリーチョイスシステムを活用し、設備を暮らしに合わせて選べる自由度の高さが魅力。
断熱×太陽光発電で
エネルギーを活かしたいなら

-
高断熱×太陽光発電で、
省エネ&快適な暮らしを実現
断熱等級7に対応した高断熱構造を採用。外気の影響を受けにくいため、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住環境を実現。さらに、太陽光発電を標準搭載し、光熱費を抑えながらエネルギーを効率的に活用 できる。 -
停電・断水時も安心!
災害時の備えにも対応
万が一の停電時には、太陽光発電+蓄電池で電力を確保し、普段と変わらない生活が可能。また、断水時でも約6日分の生活用水を確保 できるため、ライフライン確保にもつながる。
IoTで家電をコントロール!
スマートに暮らしたいなら

-
「IoTで家電&エネルギーを
管理し、快適な暮らしを実現」
アイ工務店のIoT住宅は、スマホやAIスピーカーで家電を操作でき、外出先からエアコンや照明のON/OFFが可能。また、分電盤に設置された電力センサーで家全体の電力使用状況をリアルタイムで確認し、無駄な電力を抑えて節電&家計管理にも活用できる。 -
無駄のない動線設計で、
ストレスフリーな暮らしを実現
家族の動きを考えた「おかえり動線」や「回遊動線」を採用し、生活の流れをスムーズに。最短ルートで移動できる設計により、家族の移動ストレスを減らせる住まいを実現。